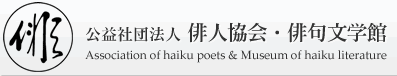今日の一句
- 四月十七日
古寺にしろがねの雨松の花 池内けい吾 松山の自宅に近い観月山にある石雲寺は、富安風生ゆかりの寺。境内に風生堂もある。松の花に、春驟雨がきらきらと光った。
「池内けい吾集」
自註現代俳句シリーズ八(四七)
- 四月十六日
さみしさを笑みもてぬぐふ桜貝 三田きえ子 モナリザの微笑とまでゆかなくとも、ほほえみは心の屈折をカムフラージュする。
「三田きえ子集」
自註現代俳句シリーズ七(一四)
- 四月十五日
はまぐりの殻に遠景らしきもの 櫂 未知子 神田育ちの父は上京すると蛤つゆを飲みたがった。あの殻にあるぼんやりとした景色は、早くに亡くなった父との最後の光景のような――。
「櫂未知子集」
自註現代俳句シリーズ一二(四一)
- 四月十四日
遍路の歩たゆまず淵を一顧せず 佐野まもる ひたすらなる遍路の歩は、碧くたたえる淵など一顧することもない。ただもうお大師にすがって一心不乱の旅をつづけるだけだ。
「佐野まもる集」
自註現代俳句シリーズ三(一六)
- 四月十三日
木の芽風大屋根に人のぼりゐる 雨宮きぬよ 我町は坂の町でもある。見晴らしがきく。
「雨宮きぬよ集」
自註現代俳句シリーズ一一(一一)
- 四月十二日
花時の赤子の爪を切りにけり 藤本美和子 「赤子」は生後一か月頃の初孫。「花時」の季語に赤子を抱いた時の感触やら、爪の色等々がまざまざと蘇る。その孫も今春、はや大学生である。
藤本美和子
二〇〇七年作。『天空』所収
- 四月十一日
かがやきてわが頬かすめ落花あり 志村さゝを 第二の人生。設置者、県より委託される福祉施設を管理する法人に、退職の翌日採用された。
「志村さゝを集」
自註現代俳句シリーズ七(八)
- 四月十日
花の雨弔詞は常に口籠る 貞弘 衛 生前の輝かしい業績や、立派な人柄を、如何に讃えても、厳粛な霊前に告別の辞を述べることは、誰でも、口籠らざるを得なくなるのだろう。
「貞弘 衛集」
自註現代俳句シリーズ三(一五)
- 四月九日
花ちるや瑞々しきは出羽の国 石田波郷 「馬酔木の最後の仕事を持つて蔵王高湯温泉に赴いた。水原先生の御好意に依る。東京は葉桜であつたが出羽の国は満開の花、山は尚蕾が固かつた。帰途車中の作」。波郷はこの頃に馬酔木の編集並びに同人を辞している。
「石田波郷集」 脚註名句シリーズ一(四)
- 四月八日
秘仏ただ黒しと甘茶そそぎけり 薮内柴火 嵯峨清涼寺の甘茶仏は仏生会のときだけ開帳され、法要が終ってから一般に灌仏が許される。恐る恐る甘茶をそそいだが、黒いばかりであった。
「薮内柴火集」
自註現代俳句シリーズ六(二)
- 四月七日
さくら餅買うて暮光を手離さず 本宮哲郎 さくら餅の匂いをそっと抱いて薄暮を帰る。春を先取りしたような、ささやかながらリッチな気分。
「本宮哲郎集」
自註現代俳句シリーズ一一(八)
- 四月六日
桜咲く磯長の国の浅き闇 原 裕 磯長の国は既出。この太平洋に面した一帯には濃密なくらさといったものはなく、桜の咲くころともなるといっそう淡々とした闇がたちこめる。
「原 裕集」
自註現代俳句シリーズ一(二四)
- 四月五日
そそくさうきうき野良連の花見連 平畑静塔 宇都宮市八幡山の花見風景。昭和三十七年、関西より移住した作者には、北関東の風物にはかなりの違和感があったのであろう。醍醐の花見、吉野の花見に馴染んだ作者には、県都のど真ん中の花見も、こういう感じがしたのであろう。自註には女連の花見とある。(宋 岳人)
「平畑静塔集」 脚註名句シリーズ二(三)
- 四月四日清明
桜の夜鋼索黒き油垂れ 藤井 亘 夜桜の千光寺へ往復するロープウェイの灯の函が、宙で交叉する美しい夜景。暗いところでは滑車が汚れた重油を垂らしていた。
「藤井 亘集」
自註現代俳句シリーズ五(五一)
- 四月三日
風の髪ふんはりと来て夕桜 角川照子 夕桜、一日中の緊張から解放された桜が一番好き、桜を渡って来た風が私の髪に宿ってふんわりと。夢幻のとき。
「角川照子集」
自註現代俳句シリーズ五(一三)
- 四月二日
咲きやうの乙女さびたる糸桜 伊東 肇 砧公園の中を流れる野川のほとりに、魅了してやまない枝垂桜がある。毎春、この糸桜だけを見るために出かけてゆく。
「伊東 肇集」
自註現代俳句シリーズ一一(三八)
- 四月一日
がうがうと水音迫り初桜 鈴木厚子 初桜に、水音ばかりが迫っていた。
「鈴木厚子集」
自註現代俳句シリーズ一一(五三)
- 三月三十一日
税金が返つてくるよ桃の花 草間時彦 納税期、確定申告は、新季語として少しずつ認められつつある。確定申告のあと、しばらくして税金の還付通知が来ることもある。もとは自分のお金とはいえ、納めた税金が戻って来るのは一種格別な気持である。〈税申告気になつてゐる寝酒かな〉。(山崎ひさを)
「草間時彦集」 脚註名句シリーズ二(一)
- 三月三十日
春茸を干し足音の澄める村 神尾季羊 椎葉の鶴富屋敷。平家の血すじだという老婆が、伝承の書簡や巻物などを見せてくれた。真昼しずかな庭に一筵の春茸が干してあった。
「神尾季羊集」
自註現代俳句シリーズ四(一七)
- 三月二十九日
外厠戸がぎいと鳴り春の山 山上樹実雄 宇陀から室生へ赤埴の集落を過ぎてすぐの山間に仏隆寺がある。かつての隠れ里も今は古木の大桜へ物見の車が集まる。急に厠の戸が、春の風だ。
「山上樹実雄集」
自註現代俳句シリーズ五(五五)
- 三月二十八日
職退けば一国鉄の東風の駅 亀井糸游 これまでは職場のつづき、わが社の駅と見ていたが、今日からはそうはいかぬ。三十余年間の国鉄生活を離れた覚悟と感懐。
「亀井糸游集」
自註現代俳句シリーズ二(一三)
- 三月二十七日
職退いて疎遠椿の花蕾 木村里風子 同僚が退職したが一年位は時々顔を出していた。いつのまにか来なくなった。
「木村里風子集」
自註現代俳句シリーズ一一(一二)
- 三月二十六日
木下ろしの痕ありありと春の山 染谷秀雄 紫陽花の葉が出始めた三室戸寺へ向かう。境内には蓮の甕が累々と並ぶ。木下ろしをした痕が長々と付いている宇治の春の山を近くに見た。
「染谷秀雄集」
自註現代俳句シリーズ一三(二八)
- 三月二十五日
雑木の芽日に日に名乗りあげにけり 小浜史都女 葉を落していた樹木が春の訪れとともに芽吹いてきた。裸木ではわからなかった木の名前が芽吹きとともに私たちに教えてくれる。
「小浜史都女集」
自註現代俳句シリーズ一一(三四)
- 三月二十四日
謡ふ父見え朧夜の続きをり 小川かん紅 小学校三年生の時に失った父の記憶は、数えるほどしかない。見台の前に端座して独得の節まわしで唸っていた父の面影はよく覚えている。
「小川かん紅集」
自註現代俳句シリーズ八(四八)
- 三月二十三日
落椿芯に小穴の抜けてをり 松永浮堂 三月、研修も終盤。教員仲間と箱根での研究会に参加した。宿の近くで落椿を見つめる。見つめることこそ俳句の基本。落椿は美しくも虚しい。
「松永浮堂集」
自註現代俳句シリーズ一二(六)
- 三月二十二日
外梯子濡るる春雪降るかぎり 田村了咲 二階建てのアパート、何世帯か住んでいる。淡雪が降って、外梯子を濡らす。外梯子だから当然なことだが、春の雪に濡れるのは何か悲惨である。
「田村了咲集」
自註現代俳句シリーズ二(二二)
- 三月二十一日
唄ふごと魚糶る声や燕来る 伊藤秀雄 何処の漁港でも糶場は活気があり、句作の狙いどころである。呪文のようにも聞こえ、あれで糶が出来るのかと感心する。
「伊藤秀雄集」
自註現代俳句シリーズ一三(一)
- 三月二十日春分
風に歩む前歯つめたし卒業期 坂本宮尾 卒業は何かの業に終止符を打つことであるが、それはまた新世界への船出でもある。三月は別れと新たな出会いへの感慨と緊張に満ちている。
坂本宮尾 『別の朝』平成十八年
- 三月十九日
ひと組の板桶となり鳥雲に 中村雅樹 東海道五十三次の四十七番目の関宿。ここで「関の山」という言葉が生まれた。桶を作っている店があり、その様子を興味深く眺めたものである。
「中村雅樹集」
自註現代俳句シリーズ一三(二〇)