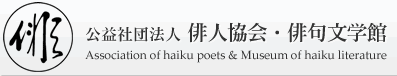今日の一句:2019年06月
- 六月一日
なつかしき記憶にラジオ電波の日 大坂晴風 昭和の初め頃はラジオのある家庭は少なかった。我が家に無く知人宅に聞かせて貰いに行ったものである。今でも思い出される。今日は電波の日。
「 大坂晴風集」
自註現代俳句シリーズ一一( 五五)
- 六月二日
ベレー帽揃ひの赤や開山祭 大原雪山 上高地・ウェストン祭。毎年六月第一日曜日、ウェストンのレリーフの前で行われる。健脚者は徳本峠を越えて参加。さわやかな集まり。
「 大原雪山集」
自註現代俳句シリーズ一一( 三六)
- 六月三日
蠅生れて以後と以前とをわかつ 加倉井秋を 蠅の生まれる前とそれ以後は身辺は何となくざわめく。夏への思いを、蠅に託した一句。身辺で感じた世の不安さがこんな句にも胎ったと言える。
「 加倉井秋を集」
自註現代俳句シリーズ二( 一一)
- 六月四日
水飲んでみんな健康青嵐 原田かほる 同じ年に〈 水飲みて人老いやすしさくら時〉の青児句がある。
「 原田かほる集」
自註現代俳句シリーズ一一( 二四)
- 六月五日
梅雨寒や教師へそくり話して 藤井吉道 教師もやはり人間。人間であればこそ自己の身分を忘れた行動に出ることがしばしばある。それを客観的に見たときには滑稽に見える。
「 藤井吉道集」
自註現代俳句シリーズ一一( 二五)
- 六月六日芒種
芒種はや人の肌さす山の草 鷹羽狩行 気づかなかった指の切傷。「 芒種」は六月六、七日ごろ。芒( のぎ)ある穀物を播くべき時という意味で、田植も始まる。
「 鷹羽狩行集」
自註現代俳句シリーズ・続篇七
- 六月七日
五月雨や田にも山にも神まして 光木正之 農業も機械化が進んだが、田植どきになると、神とのかかわりの名残と思われるものが多い。
「 光木正之集」
自註現代俳句シリーズ一一( 二三)
- 六月八日
かたつむり初めて通る枝ならむ 中村菊一郎 このかたつむりの歩みは、格別鈍かった。初めて通る不安があるのだろうと解釈した句。この句は総合誌に載ったので種々の意見をいただいた。
「 中村菊一郎集」
自註現代俳句シリーズ一一( 二二)
- 六月九日
紫陽花や大河のごとく潮流れ 山川安人 長門壇ノ浦。長く外部へ赴任していたので、一緒に行く誘いもなく、一人疎外感に浸った旅。
「 山川安人集」
自註現代俳句シリーズ一一( 二七)
- 六月十日
時の日の時を惜しんで打つメール 杉 良介 現代人は携帯メールの擒になってしまった。その味を覚えると病みつきになる。もう峠は越えたれども。
「 杉 良介集」
自註現代俳句シリーズ・続篇二七
- 六月十一日
塔照らす灯にひらひらと蚊喰鳥 川澄祐勝 塔の投光器が点く頃には沢山の蝙蝠が舞い始める。光に集まる虫を狙うらしく頻りに光線を過る。飛び方がつたないのが愛嬌である。
「 川澄祐勝集」
自註現代俳句シリーズ・続篇二二
- 六月十二日
こぼさじと手のひらに椀ぐゆすらうめ 藤沢樹村 調布にいたとき母が植えた山桜桃の木を、八王子の今の家に移植した。実が成ると仏壇に供える。あとは鵯が来てよろこんで食べる。
「 藤沢樹村集」
自註現代俳句シリーズ一一( 四一)
- 六月十三日
女学生かくさんざめき桜桃忌 江口井方 地下鉄に賑やかな女学生の一団が乗り込んできた。そういえば太宰治の忌。
「 江口井方集」
自註現代俳句シリーズ一一( 二八)
- 六月十四日
紺屋町藍の匂ひの溝浚ふ 下里美恵子 足利は織物の町。紺屋が並ぶ町筋は、溝がきれいに凌ってあった。芥からかすかに藍の匂いがした。
「 下里美恵子集」
自註現代俳句シリーズ一一( 四九)
- 六月十五日
お田植祭足駄痛しと猿田彦 佐藤俊子 会津の伊佐須美神社のお田植は、日本三大お田植の一つ。神社よりお田植田まで長い距離があり、一枚歯の高足駄で先頭を進む。
「 佐藤俊子集」
自註現代俳句シリーズ一一( 四六)
- 六月十六日
父の日の夫に鱶鰭スープかな 渡辺雅子 母の日より一ヶ月遅れの父の日、すなわち六月は夫の誕生日でもあり、息子家族と連れ立ちて津田沼アスターへ。ささやかな会食。
「 渡辺雅子集」
自註現代俳句シリーズ一一( 二六)
- 六月十七日
うるはしき山あぢさゐに小夜の雨 関根喜美 深山のあじさいは色が濃く葉には雨つぶがひかっていた。
「 関根喜美集」
自註現代俳句シリーズ一一( 一三)
- 六月十八日
出港のテープ伊達めく夏手套 木村里風子 日焼け防止用の白い手袋、この時代では働く姿が本意であった。広島港で所見、有閑マダムに見えた。
「 木村里風子集」
自註現代俳句シリーズ一一( 一二)
- 六月十九日
箱振つて大歳時記の夏を出す 松倉ゆずる 寒がりでその分夏が好きな男の顔が見えているかしら。歳時記は夏の部が最も厚いのだ。
「 松倉ゆずる集」
自註現代俳句シリーズ一一( 二一)
- 六月二十日
短夜や軒うつて雨衰へず 村田 脩 早暁、軒うつ雨音の意外に大きな響きに、明るさにもかかわらずまだ降り募る雨を感じていた。
「 村田 脩集」
自註現代俳句シリーズ三( 三五)
- 六月二十一日
空海の月命日や栗の花 西山小鼓子 小庵近くの立江堂は百年前阿波より分霊を迎えた堂で、六月二十一日改修落成式があり句額を献じた。上海の葛祖蘭、蔡蓉曽両氏の投句もあった。
「 西山小鼓子集」
自註現代俳句シリーズ五( 三二)
- 六月二十二日夏至
夏至の日の家居いづくに立つも風 岡本 眸 狭い家の中を行ったり来たりして朝の掃除。足首に風が這うように触れる。夏も本番近い。
「 岡本 眸集」
自註現代俳句シリーズ二( 一〇)
- 六月二十三日
親指でこすつて梅雨の眼鏡かな 八木林之助 唇の厚い牛山一庭人が珍しく句会に来ている。憮然とした顔で、短い指で直に眼鏡を拭いている。よけい曇らないのかなと思って見ていた。
「 八木林之助集」
自註現代俳句シリーズ三( 三七)
- 六月二十四日
甘藍に等しき日ざし巻き始む 雨宮昌吉 キャベツ畑での写生感慨句。殆どすべてが一斉に「 卷き」の兆しを見せていて、人また孜孜たるべしとの思いを深くした。
「 雨宮昌吉集」
自註現代俳句シリーズ四( 三)
- 六月二十五日
鯖鮓やいづうに昼の舞妓たち 村山古郷 「 いづう」は京都花見小路にある京鮓の老舗。ふだん着で素顔の舞妓たちが、楽しげに語らいあいながら、鯖鮓を食べていた。
「 村山古郷集」
自註現代俳句シリーズ三( 三六)
- 六月二十六日
ステテコや雨となりたる紐ゆるみ 村上しゅら 私は、ステテコが好きだ。暑い日は、ステテコに半袖シャツで店番をして妻に叱られた。
「 村上しゅら集」
自註現代俳句シリーズ三( 三四)
- 六月二十七日
萍や湖といへども流るなり 岩下ゆう二 熊本市近郊の江津湖。湖といっても、流れ込んだ水がまた流れ去って行く過程での湖。水は流れる。萍も流れる。静かだが動いている湖だ。
「 岩下ゆう二集」
自註現代俳句シリーズ四( 一一)
- 六月二十八日
万緑の中きらきらと修羅落し 今井つる女 同じく阿波路。伐採した材木を、一挙に山の急坂を落して運ぶ。木の間を遠くきらきらと光りつつ落下するさまは壮観であった。
「 今井つる女集」
自註現代俳句シリーズ四( 一〇)
- 六月二十九日
反抗期とて夏服の子の背丈 大津希水 高校の子が口答えが目立つようになった。背丈も急に伸びて叱っても子供とは一寸勝手が違う。反抗期という言葉を思い出して気にもかけないが。
「 大津希水集」
自註現代俳句シリーズ四( 一三)
- 六月三十日
竹皮を脱ぐや俳諧脱皮せん 竹腰八柏 木曾の旅。円空仏を訪ねて等覚寺に至る。付近の藪に今年竹を見る。成長の為の脱皮。俳句また然りである。
「 竹腰八柏集」
自註現代俳句シリーズ五( 二〇)