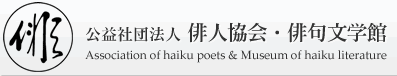今日の一句:2024年12月
- 十二月一日
石蕗咲くや心魅かるる人とゐて 清崎敏郎 珍しく恋の気配のある一句。これが発表された時、女弟子たちはどなたのことだろうと言い合ったものだ。石蕗という淋しげな花がすべてを語っている。作者は、「ある尼さんだよ」とおっしゃったが、季題からの想像を楽しみたい。(西村和子)
「清崎敏郎集」 脚註名句シリーズ二(二)
- 十二月二日
四隣みな根雪待つかに静かなり 細谷鳩舎 農家も商家も、雪囲やその他冬の準備が終ると、静かになる。運命のように雪籠りを待つのである。
「細谷鳩舎集」
自註現代俳句シリーズ五(三四)
- 十二月三日
寄鍋や婦唱に夫随とはならず 関森勝夫 料理となれば普通は婦唱夫随だろう。しかし、私は素直に従わず、具について注文をあれこれ出しては妻や子供から嫌われる。
「関森勝夫集」
自註現代俳句シリーズ六(二四)
- 十二月四日
牛鬼の壁に掛けある冬座敷 髙崎トミ子 宇和島は牛相撲で有名らしいが、私たちが宇和島へ訪れた時はその時季ではなかった。それでも二宮さんの手配りで牛相撲の土俵を見学出来た。
「髙崎トミ子集」
自註現代俳句シリーズ一一(三一)
- 十二月五日
山間の狐火となる一輌車 関口恭代 一輌車、現在では殆ど見かけないが、遠い昔上信電鉄の一輌車が山間を縫って終点下仁田までの往き来。真っ暗な山裾に動く一筋の灯、まさに狐火。
「関口恭代集」
自註現代俳句シリーズ一一(九)
- 十二月六日
行僧を入れて寒林緊りける 毛塚静枝 中山法華経寺の荒行は十一月一日から翌年の二月十日までの百日間。小寒から大寒へと森の中で、一日二度の粥食、七度の水垢離に耐える荒行。
「毛塚静枝集」
自註現代俳句シリーズ一〇(一二)
- 十二月七日大寒
裸木のざくりと折れて風いまだ 源 鬼彦 寒地の冬の木は、裸木という強いひびきが似合うようだ。寒林の中の数本が無慚に折れている。風に代表される援軍すらもないまま。
「源 鬼彦集」
自註現代俳句シリーズ一一(四四)
- 十二月八日
歳晩の孫をあづかる一日あり 五十嵐播水 歳晩になると誰しも忙しい。歳晩の一日孫をあずかってくれと頼まれた。歳晩には何うしてもこんな日があるものである。
「五十嵐播水集」
自註現代俳句シリーズ四(五)
- 十二月九日
しみじみ孤り寝ても覚めても隙間風 小松崎爽青 孤独感を口にすることはあったが、孤独地獄にまで引き込まれたことはなかったのに、家の中に全くの孤り暮しは、遣る瀬無かった。
「小松崎爽青集」
自註現代俳句シリーズ七(五)
- 十二月十日
悪魔のための空席一つ冬の酒 磯貝碧蹄館 花も何も飾ってない、殺風景な席は悪魔の席かもしれない。いや、むしろ「悪魔の席」として、私はとって置きたい。親愛なる悪魔のために。
「磯貝碧蹄館集」
自註現代俳句シリーズ三(二)
- 十二月十一日
ストーブに来し入港の船の影 永田耕一郎 赤々と燃えているストーブ。入港の巨船の影が、これ程大きいとは思いがけなかった。
「永田耕一郎集」
自註現代俳句シリーズ五(四六)
- 十二月十二日
偕老の片身さまよふ虎落笛 久保千鶴子 「俳句未来」所載句より。入院して運動リハビリのある日、今日はきつくて死ぬかと思ったと帰室、苦笑した瞬間、脳梗塞で倒れた夫。
「久保千鶴子集」
自註現代俳句シリーズ八(一一)
- 十二月十三日
なすままにけふのみ仏煤払ふ 藪内柴火 万福寺の煤払である。本尊の釈迦牟尼仏をはじめ諸々の仏が、今日ばかりは煤払いの僧のなすままに身をまかせて在すように拝された。
「藪内柴火集」
自註現代俳句シリーズ六(二)
- 十二月十四日
さくら炭惜しまず義士の日を修す 山田孝子 十二月十四日の義士会に参じた。雪ならぬ雨に悴みながら墓に詣で巴紋の茶碗で抹茶を頂き、蕎麦を啜り討入の日を偲んだ。
「山田孝子集」
自註現代俳句シリーズ八(三九)
- 十二月十五日
白鳥のたよりのとどく青邨忌 坂本宮尾 師山口青邨が96歳の大往生を遂げたのは昭和63年12月15日。この季節になると盛岡の句友から、白鳥も来ていると吟行の誘いを受ける。
坂本宮尾 2018年11月 パピルス冬号に発表
- 十二月十六日
落武者の如くに憩ひ枯野行 成瀬正俊 祖先にゆかりある三河の野を歩いてゆく。遠い道を歩いて疲れると、道端に腰を下して休んだりして歩いてゆく。落武者のようにとぼとぼと。
「成瀬正俊集」
自註現代俳句シリーズ四(三六)
- 十二月十七日
生姜糖の天秤量り年詰まる 松本 翠 浦和の年の市(十二日町)の雑踏。公園内の見世物小屋に入って興じてみたりした。
「松本 翠集」
自註現代俳句シリーズ九(一八)
- 十二月十八日
杖もまた足の一本十二月 竹村良三 だんだん杖が離せなくなってきた。
「竹村良三集」
自註現代俳句シリーズ一三(九)
- 十二月十九日
師走の歩緩急いづれにも添はず 貞弘 衛 この句は、日常万事に平常心是道を、問わず語りに表白した内外両面に渉る自画像と畏友から過褒を得たが、まだ願望に過ぎない。
「貞弘 衛集」
自註現代俳句シリーズ三(一五)
- 十二月二十日
葱めづる詩が鐵めづる詩に續く 相生垣瓜人 高村光太郎の詩に因って作った。葱と云う物と鉄と云う物を並べると二つの物の間に相背き相惹く気の様なものが生れるのに興味を覚えて詠んだ。
「相生垣瓜人集」
自註現代俳句シリーズ一(一九)
- 十二月二十一日冬至
鹿ヶ谷南瓜ごろごろ冬至かな 金久美智子 平家追討の密議があったのが鹿ヶ谷で、瓢箪型に縊れた縮緬南瓜が京都特産で、近くの農家の小屋に沢山あった。料亭で食べると美味しいが......。
「金久美智子集」
自註現代俳句シリーズ一一(四五)
- 十二月二十二日
乳石に枯野の日ざしさすばかり 高久田橙子 鏡石町深内の乳石神社に、石の男根女陰が祀ってある。女陰が乳石と崇められ、産婦がお参りすると乳が出ると信じられている。
「高久田橙子集」
自註現代俳句シリーズ五(四五)
- 十二月二十三日
愛日といふ言の葉を胸の奥 藤本美和子 「愛日」とは「冬日」の傍題に載る季語。「冬のありがたい太陽」のことと知り、以来心に留めている。
藤本美和子 二〇一七年作 『冬泉』所収
- 十二月二十四日
聖しこの夜古き灯もらす写真館 佐野まもる NHKの「夏ちゃんの写真館」は、この時代にはまだこの句のようであった。今思い出してみると泣きたくなる程のなつかしい町並みだった。
「佐野まもる集」
自註現代俳句シリーズ三(一六)
- 十二月二十五日
煉炭火鉢に聖樹を植ゑて山谷街 大場美夜子 浅草の山谷は自由労務者の人達の宿が並んでいる街で有名、観音様から廻ってみた。仕事にあぶれた漢達が数人、クリスマスツリーを立てていた。
「大場美夜子集」
自註現代俳句シリーズ五(九)
- 十二月二十六日
鼻面に雪つけ栗毛丸太曳く 阿部幽水 原木丸太に鎹を打ち、馬の玉曳き。官林の造材風景。
「阿部幽水集」
自註現代俳句シリーズ八(三一)
- 十二月二十七日
肩あげの厚かりし日よ遠雪嶺 平井さち子 遠い山襞の雪の陰翳が、ふと昔を甦えらせる。綿入の着物の肩あげや腰あげのふくらみと、あの感触を。
「平井さち子集」
自註現代俳句シリーズ三(二八)
- 十二月二十八日
数へ日の夜汽車のひとりひとりかな ながさく清江 師走も押し詰まった夜汽車。そのひとりひとりが、今年一年の締め括りへ、それぞれの思いを抱いた表情の黙を、汽車は只運んでゆく。
「ながさく清江集」
自註現代俳句シリーズ一一(六〇)
- 十二月二十九日
白鳥千羽東にひらく海と空 成田千空 師草田男に白鳥をよんだ名句があるように、千空にも佳句が多い。句集未収録の〈白鳥の啼かんとす頸ほそりけり〉(昭和二十二年)が初めての作。陸奥湾浅所海岸は全国に知られた飛来地で、掲句もそこでの景。平成十年その地に句碑として建立された。(新谷ひろし)
「成田千空集」 脚註名句シリーズ二(七)
- 十二月三十日
夜の手に落ちし楢山十二月 森川光郎 楢山は一年をとおして好きだ。日が暮れて、暗い楢山、年が迫っていた。
「森川光郎集」
自註現代俳句シリーズ一二(一五)
- 十二月三十一日
紺つよき大洋に倚り年送る 原 裕 太平洋に向って開かれた相模湾の一角にある丘の上から、紺碧の沖をみつめる。水平線上に浮き出た大型の船とともに三十代最後の年が過ぎゆく。
「原 裕集」
自註現代俳句シリーズ一(二四)